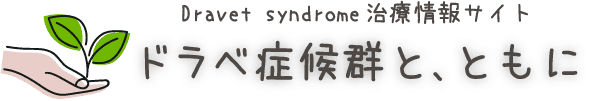- 初めての発作
- 生後3か月のとき、発作が止まらなくなり、救急車を呼ぶことに。
-
生後3か月、2種類のワクチン接種を受けた晩のこと。微熱があったのでワクチンの副反応かと思っていたら、夜中に一瞬ピクピクしたのです。おかしいと思いつつ気に留めずにいると、明け方、全身が小刻みに震えだし、発作が止まらず意識がない状態が続いたので救急車を呼ぶことに。搬送先の病院で入院して検査したもののその時点では発作は見られず、「胃腸風邪と熱性けいれんでは」と言われました。
- 発作が止まらない…
- 発作が止まらず、たびたび救急搬送され、てんかんと診断されました。
-
その後、発熱時や入浴中に発作を起こし止まらず、たびたび救急搬送され、てんかんと診断されました。生後4か月のことです。搬送先の病院で薬物治療を始めましたが、発作の頻度は減らず、入浴のたびに発作を繰り返しました。薬を増量したり別の薬に変更したりしましたが、発作の頻度は減らず、強直間代発作が起こるなどして、改善は見られなかったのです。
- 「ドラべ症候群」診断
- ドラべ症候群と確定診断され、2~3歳の頃に発作が群発。いちばん深刻な状況でした。
-
以前から、主治医の先生に「ドラベ症候群かもしれない」と言われていました。そこで遺伝子検査を受け、1歳6か月のときに確定診断されました。ただ、薬を飲んでも発作は一向に落ち着かず、2〜3歳の頃は発熱のたびに発作が群発し、週2、3回は救急車を呼んでいました。いま振り返ると、その頃がいちばん深刻な状況だったと思います。
- 治験に参加!
- 大変な時期が続く中、「発作が本当にコントロールできるなら」という一心で治験に臨みました。
-
そんな大変な時期を過ごしていたときのこと。セカンドオピニオンとして検査を受けたり、意見を聞いていたてんかん専門医療機関の先生から、新薬の治験の話がありました。娘がその対象になるとのことでしたし、私もドラベ症候群の患者家族会でその治験の情報が広まっているのを知ったので、迷わず参加を決意しました。もちろん承認前の薬への不安や迷いがなかったわけではありません。それでも「発作が本当にコントロールできるなら」という一心でした。娘が小学校にあがる直前のことです。
- 発作の減少
- 治療を進めていく中で、発作の状況に変化が現れました。
-
発作が減らなかったので、治験に参加しました。抗てんかん薬を追加したことで“目パチ”がなくなり、しばらくすると強直間代発作も見られなくなったのです。38℃台前半の発熱なら発作を起こさないことも。無熱発作もほぼなくなり、最近まで最初の用量で続けて来られました。ただ、つい最近、5年ぶりに長めの発熱発作と、2~3分ほどですが2回無熱発作が起きたため、薬を増量しました。そのほか、以前から服用している3剤は減量できています。
- できるようになったこと
- 発作がなくなったことで、私たちの生活は変わりました。
-
言葉数が以前より増え、ペチャクチャおしゃべりできるわけではありませんが、会話のキャッチボールができるようになりました。また、物事に集中して取り組む時間も長くなりましたし、体も動かしやすくなることが増えています。発作を起こしそうだからと、私たち親が制限をかけることもほとんどなくなりました。たとえば、湯船につかれるようになったことはとても大きなことです。以前は、発作が夜に出やすく、入浴のタイミングと重なっていたので、慎重になっていましたが、今では妹や弟と毎日一緒に入浴できるようになっています。体温が上がり過ぎないように部屋の温度を調節したり、薬の飲ませ方に苦慮することもなくなりました。妹弟たちにお願いしていた制限も軽くなり、特に妹は、小さいときから発作や救急搬送される姿を目の当たりにしていて、そのたびに情緒不安定になっていましたが、そうしたメンタル面での悪影響も解消できています。本人はもちろん、家族みんなの負担が本当に軽減しました。
- 生活の変化
- できることが増え、日常はガラッと変わりました。
-
発作の頻度が減ったとはいえ、やはり最初の1年間くらいは半信半疑でした。なので、少しずつ慣れて、制限を減らせるようになったという感じでしょうか。現在は、外で遊ぶのもそれほど心配することがなくなって、夜に外食に出かけたり、花火をしたり、救急車を呼ぶのがはばかられるような商業施設にも行けるように。やらせてあげられることが増えたから、できることも増えています。一日を通してみんなで活動できるようになり、日常はガラッと変わりました。
- 成長を実感
- 娘はいま、小学5年生。昔は参加できなかった行事に今はたくさん挑戦できています。
-
娘はいま、特別支援学校に通う小学5年生。クラスのお友達の名前をたくさん覚えられるようになっています。それに、係の活動を率先して引き受けるなど、みんなをリードする存在に。お姉さんとしての振る舞いもできているようです。また、昨年の宿泊学習は、みんな一緒に布団を敷いて泊まることができました。不安はありましたが、この経験は本人にとって特別だったと思います。保育園のときは参加できなかった行事がたくさんあったので、娘の成長を実感しています。
- 情報の集め方
- 病気のお子さんをもつママたちの知識にも支えられていました。
-
いまでは情報収集することが少なくなりましたが、診断されてから3年くらいは患者家族会のホームページや患者さんご家族のブログなど、いろいろ見ていました。SNSの発信の中でも特に病気のお子さんをもつママたちは知識が豊富なので、そうした情報は治療方針について先生と相談するときにとても役立ちました。
- 挑戦したいこと
- 現在は、家族みんなでのお出かけを計画しているところです。
-
メインは基幹病院の主治医の先生で、てんかん専門医療機関の先生には年1回、検査でお世話になっています。また、救急病院にも担当医がいて、救急時以外も定期的に受診しています。さらに学校や利用している2つのデイサービスとも発作時の対応について連携しています。
こうした診療・支援体制もあり、家族みんなでのお出かけを計画しているところです。たとえば、泊りがけの旅行、飛行機に乗ること、銭湯や温泉に行くことなど。本人の喜ぶ姿が目に浮かびます。
- メッセージ
- 治療にお困りのみなさんへ:
希望を信じて、前向きに治療を受けることが大切だと思います。 -
新しい治療を始めたり、治験に参加するのは、副作用のことなど不安や心配が当然あるでしょう。でも、試してみなければ分からないので、ポジティブな気持ちで考えたほうがいいのでは。治療の主導権は医師側にあると思いがちですが、先生は家族と一緒に親身になって考えてくれて、最終的には「ご両親はどうされたいですか?」と聞いてくれると思います。情報収集を欠かさず、希望を信じて前向きに治療を受けることが大切だと思います。