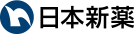社外取締役4名が、現在の課題や第七次5ヵ年中期経営計画の実現に向けた方向性について議論を交わしました。「ウプトラビ」の特許満了が迫る中で、研究開発のスピードアップ、グローバル展開の強化、経営陣の育成とガバナンスの強化などの課題に対し、各取締役から率直なご意見をいただきました。
企業文化を維持しつつ変化への対応力を期待

日本新薬には、「ひとりのために、本気になれるか。」というメッセージがあります。それを実践するために目指す姿勢と意識について社員が自主的に制定した「NSMind」は、経営の全体像の一部に組み込まれています。社員のエンゲージメントが感じられる素晴らしい文化だと思います。
「プラチナ企業TOP100」※1の調査で、日本新薬は8位にランクインしました。働きがいは成長につながり、社員の成長が会社の成長につながることが重要です。経営陣や上司の考えを社員が共有し、同じベクトルを合わせて個々が成長し、大きな力となっていくことを期待しています。
創薬や導入に関する競争が激化しており、事業の国際化に伴って業績に影響する外部要因も多様化してきています。成長を支援するために、会社は対面研修やデジタル学習など、様々な機会を提供していますが、社員満足度が高い現在の良い文化を大切にしつつ、変化に対応できる人財を育成し、採用することが必要です。
研究や製造の現場では、外部からの刺激で新しい発想やイノベーションが生まれます。多様性に富む人財を組織に取り入れ、さらなる会社の活性化に期待しています。
※1 上場企業約2,300社を対象にした日本経済新聞の調査。「プラチナ企業」とは、「働きやすさ」と「働きがい」がいずれも高い企業のこと。
中期経営計画の達成に向けて
社外視点での議論のフォローアップを図る
中期経営計画において、策定段階で社外取締役が議論へ参加する機会は多くありませんでした。開発のスピードアップについて取締役会でも集中的に議論しましたが、中期経営計画の検討と合わせて議論できるとさらによかったと思います。
私たち社外取締役は、経営における戦略的な施策や優先順位を早い段階で共有いただき、議論に参加したいと考えています。中期経営計画をボトムアップで策定する手法を取ったことは育成の一環でもありましたが、それゆえに私たちへの開示に時間がかかったのだと思います。


皆さんと同じく、骨子を作る部分から携わりたかったという思いです。中期経営計画の達成に向けて、責任を持ってしっかりフォローアップしたいと考えています。
社外取締役は、社内の議論のプロセスや会社の考え方を深く知るべきだと考えます。外部へ発信する際の見せ方に社外取締役の知見を生かすなど、社内取締役とは異なる視点でコミットできると考えています。今後は、この中期経営計画をどう実現していくかに注視し、適時議論していきたいと思います。
研究開発のスピードアップに向け、
社外取締役の知見も投入
「ウプトラビ」の特許満了というパテントクリフが迫る中、研究開発のスピード感の課題や事業価値の逸失がどの程度なのかといった、具体的な内容を討議することが増えました。
研究開発のスピードアップは、中期経営計画の「5つの経営基盤の強化」の一つであり、合議制の意思決定会議で迅速な情報共有・課題対応と徹底した進捗管理を行うこととしています。取締役会は、創薬の進捗を把握し、遅れの原因究明や対策の立案に早期に関わり、売上計画の達成の確度を上げる責任があります。
私はその意思決定会議の一員として、研究開発部門外からの点検の実効性を期待していますし、私の経験を大いに活用していきたいと考えています。フェーズ1以降の臨床試験にグローバルで取り組む際には、KOL※2の知識を取り入れ、成功確度の高い計画を立てていければよいと考えています。
私は、研究開発の観点でも成果を出すことに貪欲になり、最後までやり抜く人財が育つことを期待しています。また、次世代経営リーダーを育成する「HONKI塾」に昨年からエグゼクティブコースができて、将来の幹部候補を見極める機会ができました。
和田取締役と私は指名・報酬委員会の委員ですが、指名の部分ではまだ課題があり、経営陣の育成という点でガバナンス機能を強化する余地があると考えています。
グローバルな研究開発経験者は、こうやればうまくいくといった強い信念を持って研究にあたっています。日本新薬の皆さんにも成果の蓄積があり、双方を生かした日本新薬ならではのグローバル展開を形成していけると考えています。
専門性の高い方の雇用に向けて、ジョブ型の雇用形態の検討が進んでいます。100年以上の歴史と文化を持つ会社の中で大きな挑戦です。
同じような人財を採用しがちという採用側の課題が意識されています。経営陣の育成も含め、外部からの刺激を受け入れ、必要な人財を強化するために思い切った発想の転換が必要かもしれません。
海外販売強化については、グループ会社のNS Pharmaや研究拠点Innovation Research Partneringの体制構築が重要です。「ビルテプソ」のフェーズ3試験の結果を受け、希少疾患治療薬の開発やFDA(米国食品医薬品局)との薬事対応の経験を持つ人財の真価が問われます。米国では、患者団体がFDAに対し治療薬の早期承認を求めるなど影響力を持っており、こうした団体との関係強化が必要です。
※2 Key Opinion Leaderの略。製薬企業の販売促進に影響力を持つ医師などの専門家のこと。
危機感をバネに、
核酸医薬のトップランナーとなることを期待
日本新薬にとって今は将来の成長に向けた正念場にあると強く認識していますが、日本新薬の持つ力を結集すればきっと乗り越えていけると確信しています。社外取締役として、これまで以上に情報共有を求め、監督の実効性を強化する責任があります。
製薬の研究開発には、時間が必要です。日本新薬は、数千ある難病や希少疾患に注力していますが、導入品を見るとターゲットを絞って見極める眼力があると感じており、それが日本新薬の強みだと分かります。そういった点にも注目し、長い目で成長を見守っていただきたいと思います。

投資家からガバナンス強化に関する質問を受けることもあり、社外取締役の役割がより重要になっていると感じます。取締役会メンバーの多様化により議論が活発化しており、投資対象やROICなど、投資効率に関する議論も増えました。役員自身が株主の代表としてこの会社を管理監督し、より長期的な企業価値を高めていこうという意識が醸成されています。
国産初の核酸医薬品「ビルテプソ」を上市させたことは、日本新薬の大きな強みです。今はこの先10年のさらなる成長に向けて、新規モダリティの一つとして核酸・低分子複合体などによる創薬を目指しています。日本新薬が核酸医薬のトップランナーとなり、特長ある医薬品を創出していくことを、ステークホルダーの皆さまにも期待していただきたいと考えています。