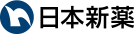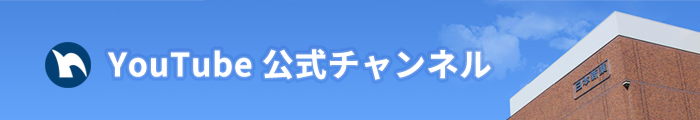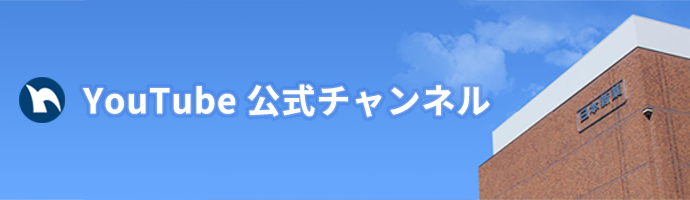基本的な考え方
日本新薬は、「人々の健康と豊かな生活創りに貢献する」という経営理念のもと、病気とともに暮らす人々に明るい未来を「共創」することを目指し、研究開発をはじめ、各部門が一体となって、医療アクセスの改善に取り組みます。社員一人ひとりが常に独自性の追求と特長のある製品の創造を目指し、他社が手掛けない領域での研究開発の推進、高品質な医薬品を迅速かつ安定的に供給する体制の整備、外部パートナーによる活動への支援、適正な情報提供に努め、医薬品を必要とするすべての患者さんにとってアクセスしやすい環境を整備します。
当社は、すべての活動において常に高い倫理性と透明性を確保し、社会の信頼に応えるため、「日本新薬グループ コード・オブ・プラクティス」を制定しています。
医療アクセス活動方針
1. 難病・希少疾患治療薬を中心とした特長ある製品の創造
いまだ治療ニーズが満たされていない領域・分野に価値ある医薬品を提供することで、人々の健康と豊かな生活創りに貢献する
2. 医薬品を必要とするすべての患者さんにとってアクセスしやすい環境の整備
必要とされる医薬品の提供に際し、様々な背景を考慮し患者さんにとってよりよい環境を提供できるよう努め、迅速かつ安定的にすべての患者さんに医薬品を供給できる体制を構築する
3. 医薬品の適正使用の推進
適正な情報提供活動による一般の方の知識向上に努め、偽造医薬品など不正な医薬品への対策に取り組む
4. 外部パートナーによる活動への支援
外部パートナーが行う活動に協働や支援を行うことで、自社だけでは成し得ない医療アクセスの改善に取り組み、必要としている全ての患者さんに医療が適切に届けられる社会の構築に寄与する
知的財産と医療アクセスが困難な国における特許における考え方
一部の国では、経済的・地理的要素等により医薬品へのアクセスが困難な地域が存在している実情があります。
当社の医薬品を必要とする一人でも多くの患者さんに医薬品を提供するため、LDC(Least Developed Countries:国連が制定した後発開発途上国)、LIC(Low-Income Countries:世界銀行が定める低所得国)へは、特許出願、特許の権利行使は行いません。
また、国際条約であるTRIPS協定(国際的な自由貿易秩序維持形成のための知的財産権の保護などを目的とする協定)にて規定されている強制実施権について緊急避難的に発動することは合理的であると認識しています。様々な状況に鑑み、強制実施権が必要な場合には柔軟に対応すべきと考えます。
LDC:後発開発途上国(LDC:Least Developed Country)|外務省 (mofa.go.jp)
取り組み
希少疾患に対する医薬品開発
現在、有効な治療法が未確立な難病・希少疾患は7,000種以上存在し、実際に多くの方が罹患されているといわれています。日本新薬では、早くからこれらの難病・希少疾患に注目した研究開発を進めるとともに、製品の価値を高めるPLCM(プロダクト・ライフサイクル・マネジメント)、他社からの導入活動やオープンイノベーション活動を推進しています。また、これまでに実施してきた臨床試験データを活用して承認が取得可能な国々への承認申請を検討していきます。
地域特性を考慮した医薬品アクセスの向上
必要とされる医薬品の提供に際し、知的財産権を行使するにあたっては、各国規制等の諸事情を考慮します。
また、各国の医療制度、保険制度、国民の生活水準等を考慮し、適正な価格により販売することを考慮します。
医療環境整備
疾患啓発および患者サポートプログラム
臨床試験は、限られた国、限られた期間で実施されており、参加できる患者さんは限定的です。そのことから、治療の選択肢がない患者さんのために、未承認国において医薬品の提供プログラムを展開しています。また、特定の専門医のみならず非専門医にも疾患および治療剤に関する情報を提供しています。患者さんがスムーズに専門医による診療にたどり着けるよう、専門医と非専門医の連携の強化を図るとともに、患者さんに向けた疾患啓発サイトや医療機関情報の提供サイトの設置、患者サポートプログラムを提供しています。
NPO法人とのパートナーシップによる支援
中低所得国等における世界の医療アクセスの課題解決に向け、NPO等とのパートナーシップのもと医療環境の整備に向け取り組みます。
疾患啓発活動
Webサイトによる啓発活動
日本新薬では、早期受診、早期診断ならびに早期治療による患者さんのQOL向上と、診断された患者さんへ疾患理解を深めていただくことを目指して、Webサイトを通じた疾患啓発と情報提供を行っています。
2017年に開設した「肺高血圧症治療サポート」では肺高血圧症の疾患、治療の解説、医療費や制度などの紹介および専門医からの動画配信を実施し、より肺高血圧症への理解を深めていただける情報を提供しています。さらに、肺高血圧症の中でも見逃されがちな強皮症に伴う肺高血圧症を注意喚起するために「知ってる?強皮症の合併症 息切れとPH」を2020年に開設、強皮症と、それに伴い発症する肺高血圧症に関する症状や検査、治療について発信しています。
また、小児神経領域では、2021年にデュシェンヌ型筋ジストロフィーの専門情報サイト「DMDを知る」を、2022年には、「ドラベ症候群と、ともに」を開設し、指定難病であるデュシェンヌ型筋ジストロフィーならびにドラベ症候群のお子さんを持つご家族の方に向けて疾患の知識や治療、日常生活のサポートなどの情報を提供しています。
そのほか、血液の病気の一つである骨髄異形成症候群の疾患、分類、予後、診断ならびに治療について解説した「骨髄異形成症候群(MDS)を知る」、アルコール依存症の紹介・断酒成功の体験記などを掲載した「アルコール依存症治療ナビ」、子宮内膜症・月経困難症の早期受診を促す「おしえて☆生理痛」、ED(Erectile Dysfunction:勃起不全)に関する誤解を解き、受診への心理的抵抗を和らげるとともにED治療薬の偽造品に関わる情報提供・注意喚起も行う「EDケアサポート」、男性の「前立腺」に関する疾患情報をまとめた「前立腺の病気を知る~前立腺肥大症、前立腺炎、前立腺がん~」、痛みを主訴とし再発の多い疾患である尿路結石症を解説した「尿路結石症を知る」などのWebサイトを運営しています。
レア・ディジーズ・デイ( Rare Disease Day )への参画
日本新薬は、2月最終日の「Rare Disease Day(世界希少・難治性疾患の日)」に合わせて、難病・希少疾患への理解を深める活動を実施しています。
難病をテーマに、専門医との対談や学生と専門医との座談会を実施し、その内容を新聞紙面で紹介しています。

市民公開講座
日本新薬では、さまざまな領域の健康トラブルについて公開講座を行っています。専門医による病気の予防や治療に対するわかりやすい解説を聞くことができます。患者さんの支援活動について、肺高血圧症や筋ジストロフィーでのWEB市民公開講座や交流イベントを継続して開催する予定です。

メディアセミナー
業界の最新情報やわかりづらい専門的な知識を伝えるために、有識者や専門医を招いて行うメディア向けの勉強会です。 疾患に関する詳細情報を理解いただき紹介されることにより、一般の方に向けた啓発活動につなげています。